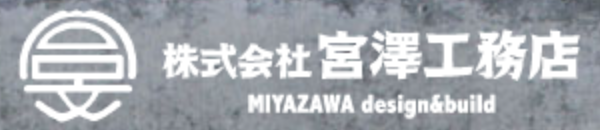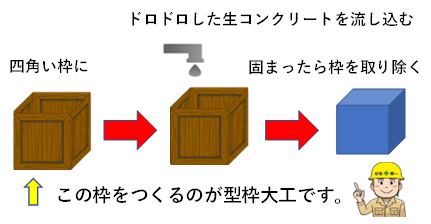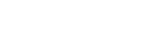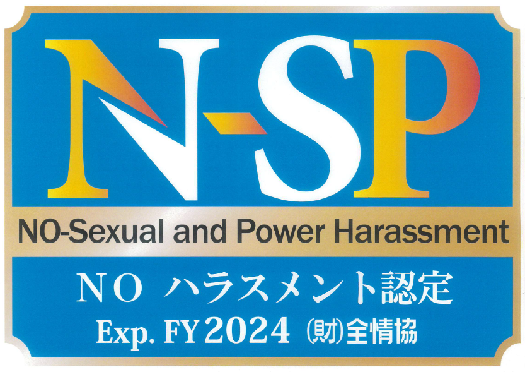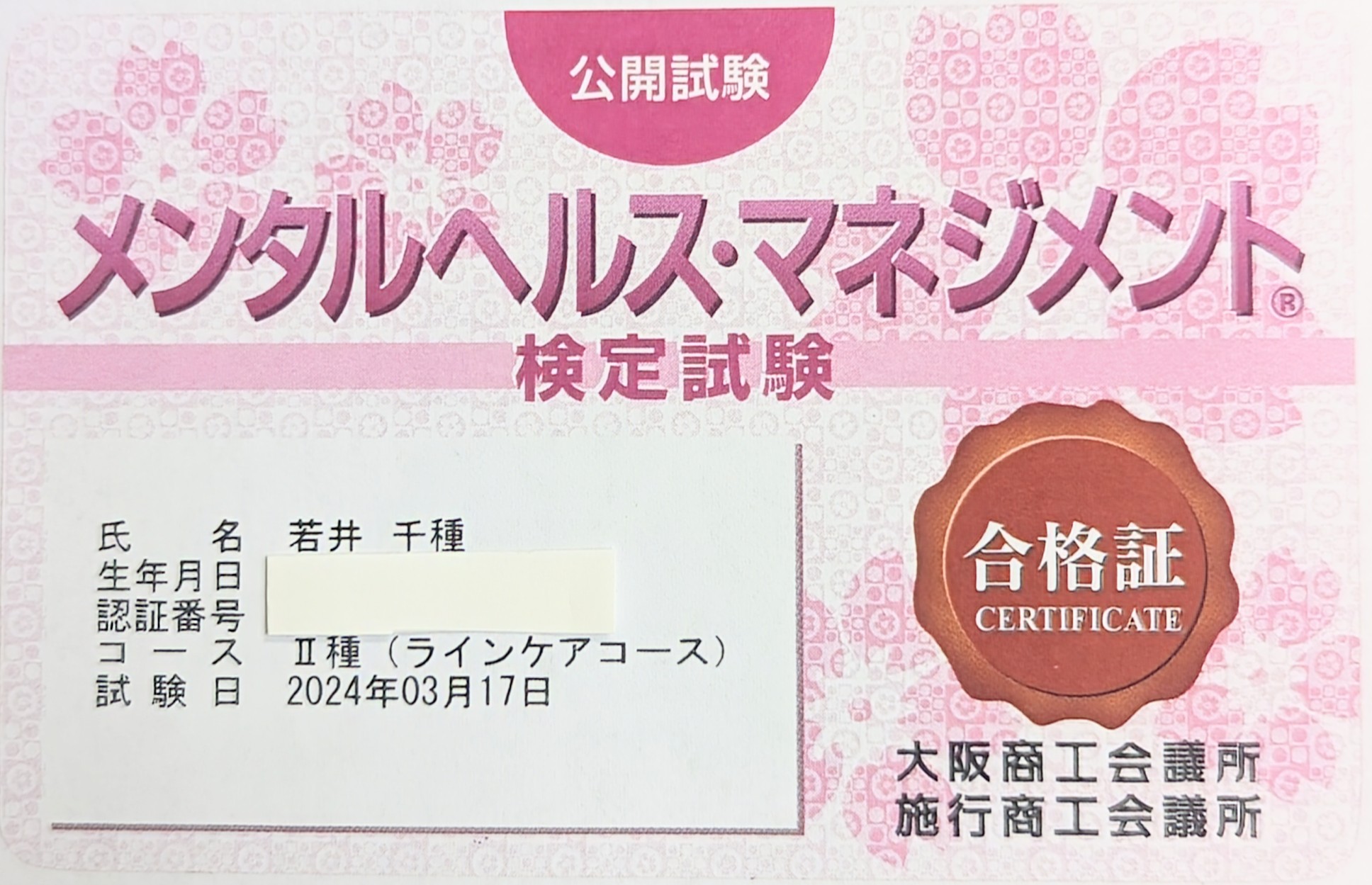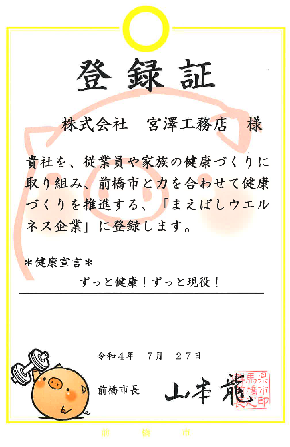2025-07-03
七夕
『七夕』は、毎年7月7日の夜に行われる日本の伝統的なお祭りです。この日は、織姫(おりひめ)と彦星(ひこぼし)という二つの星が、年に一度だけ天の川を渡って会うことを許されるという、ロマンチックな伝説が有名です。「しちせき」とも呼ばれ、古くから続く星祭りの一つとして親しまれてきました。伝説にちなんで、人々は短冊に子供の健やかな成長や学業成就、家族の健康など様々な願い事を書き、笹竹に飾り付けて星に祈ります。
七夕といえば織姫(おりひめ)と彦星(ひこぼし)の切ない恋物語ですが、この物語は、もともと中国の星伝説が日本に伝わったものです。琴座のベガと呼ばれる織女星(しょくじょせい)は、機織り(はたおり)がとても上手な働き者の娘で、鷲座のアルタイルと呼ばれる牽牛星(けんぎゅうせい)は、牛の世話を熱心にする立派な青年でした。天の神様である天帝(てんてい)は、二人の真面目さを喜んで結婚させました。ところが、結婚した二人は仲睦まじく暮らすあまり、仕事をしなくなってしまいます。織姫は機を織らず、彦星は牛の世話をしません。怒った天帝は、二人を天の川の両岸に引き離してしまい、年に一度、7月7日の夜だけ会うことを許しました。この日に雨が降ると天の川の水かさが増して渡れなくなるため、カササギが橋を架けてくれるというのもロマンチックですね。
七夕が、庶民の間にも広まったのは江戸時代で、子屋で学ぶ子どもたちが、習字の上達を願って短冊に願い事を書くようになったのが始まりといわれています。かつては機織りや裁縫、芸事、書道といった技芸の上達を願うのが主流でしたが、時代とともに七夕に込める願いも多様化してきました。現代では、学業成就、健康長寿、恋愛成就、家族の幸せ、世界平和など、本当にさまざまな願い事が短冊に託されています。短冊には赤、青(緑)、黄、白、黒(紫)の五色が使われることが多いのですが、これは古代中国の「陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)」という考え方に由来しており、それぞれの色には、意味が合込められています。
・赤:感謝の心、ご先祖様や親への想い
・青(緑):成長、徳を積む、人間力を高める
・黄:信頼、人間関係を大切にする、友人との絆
・白:義務や決まりを守る心、純粋な気持ち
・黒(紫):学業の向上、知識を得る
七夕飾りによく使われる笹竹は、とても生命力が強く、冬でも緑を保ち、まっすぐに天に向かってぐんぐん伸びる様子から、古来より神聖なものと考えられ、笹の葉が風にそよぎ擦れ合う音は、神様を招く音とも言われ、願い事を天に届けてくれると信じられていたそうです。代表的な飾りにもそれぞれ意味があります。
『吹き流し(ふきながし)』
織姫さまの織り糸を表し、裁縫や機織りの上達を願います。長寿の願いも込められています。
『紙衣(かみこ/かみごろも)』
裁縫の腕が上がり、着るものに困らないようにという願いが込められています。また、人形(ひとがた)として厄除けや災難の身代わりという意味もあります。
『投網(とあみ/とうもう)』
魚を捕る網を模した飾りで、豊漁や豊作を願います。幸運を引き寄せるという意味も。
『巾着(きんちゃく)』
昔のお財布である巾着は、金運上昇や商売繁盛を願う飾りです。節約や貯蓄の心も育みます。
『折鶴(おりづる)』
長寿の象徴である鶴を折り紙で作り、家族の長寿や家内安全を願います。千羽鶴にすると願いが叶うとも言われています。
『くずかご』
飾りを作った際に出た紙くずなどを入れるためのもので、物を大切にする心や整理整頓、倹約の精神を養うという意味があります。
七夕の夜には是非、夜空を見上げて星に願いをかけてみてはいかがでしょうか。
ハルノヒ 参照
https://harunohi.jp/680_tanabata-toha/