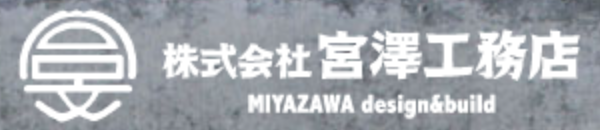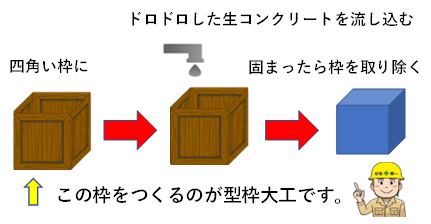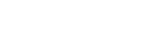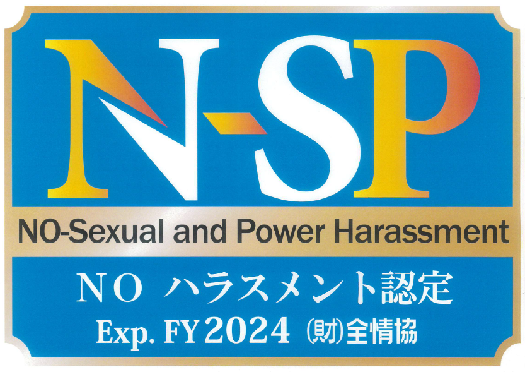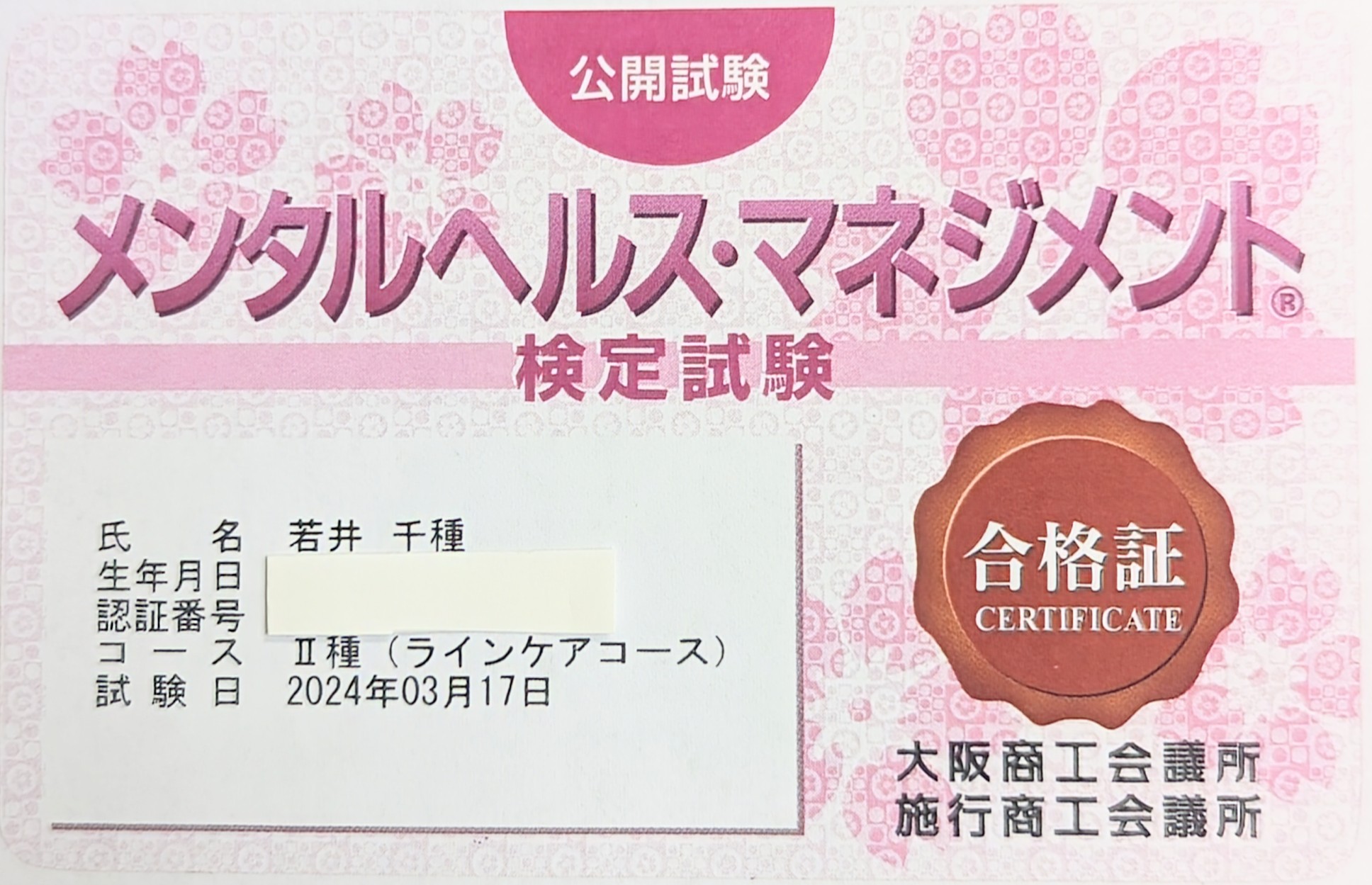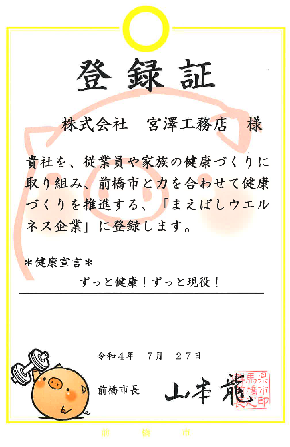2025-04-29
端午の節句
5月5日は、『端午の節句』と『こどもの日』です。『こどもの日』として祝日であり、混同しがちですがこの二つはそれぞれ違う行事です。
『端午の節句』
男児の誕生と健やかな成長を祝う行事で、もとは中国の風習です。中国では、病が流行しやすい5月は『悪月(あくげつ)』と呼ばれており、5月5日は『5』が重なるので『悪月(あくげつ)悪日(あくにち)』と言われていました。そのため、病気や厄を払う薬草と考えられている菖蒲(しょうぶ)を門や玄関に飾る『軒菖蒲(のきしょうぶ)』をしたり、菖蒲を浸したお酒を飲んだり、菖蒲湯に入るなどして厄除けと健康祈願をしていました。それぞれの季節の旬のものを食して生命力をもらい、邪気を払うという事で『五節句(ごせっく)』と呼ばれました。
『五節句』
・1月7日(人日の節句・七草の節句)
・3月3日(上巳の節句・桃の節句)
・5月5日(端午の節句・菖蒲の節句)
・7月7日(七夕の節句・笹の節句)
・9月9日(重陽の節句・菊の節句)
『端午』の『端』は物の端、つまり『始まり・最初』という意味があり、もともとは『月初めの午(うま・十二支の一つ)の日』という意味でした。後に『午(うま)』は『午(ご)』と読むことから『五(ご)』に通じることから『5』が重なる5月5日を『端午の節句』としたのが始まりだそうです。
端午の節句が日本に伝わったのは奈良時代で、当時日本では田植えの時期である5月には、五穀豊穣を祈願するために若い女性たちが神社にこもって田植え前に汚れを払う『五月忌(さつきいみ)』という風習がありました。これが中国の風習と結びついたようです。
鎌倉時代になると武道を重んじる意味の『尚武(しょうぶ)』と厄除けに使う『菖蒲(しょうぶ)』をかけて武士の間で縁起が良いと盛んになり、端午の節句は別名『菖蒲の節句』とも呼ばれるようになりました。端午の節句は、江戸時代に幕府により年間行事とされ、庶民にも広まりました。こうして江戸時代には、男の子の誕生と成長を祝う節句として定着したそうです。端午の節句には、こいのぼりや五月人形を飾って、柏餅やちまきを食べるのが一般的です。家族写真を撮ったり豪華な食事をしたり、菖蒲湯に入る風習もあります。
5月5日は『こどもの日』でもありますが、こちらは昭和23年(1948年)に制定された国民の祝日です。子供のためのお祝いの日という印象が強いですが、『こどもの人格を重んじ、子どもの幸福をはかると共に、母に感謝する』ことを趣旨としており、『こども(男の子と女の子)とお母さんの日』なのだそうです。『端午の節句』とは少し趣旨が違うようです。
どちらも違う行事ではありますが、子どもたちの幸せを願う気持ちは同じです。すべての子供たちが、幸せに健やかに成長できることを心から願っています。
日本文化研究ブログ参照
https://jpnculture.net/tangonosekku/